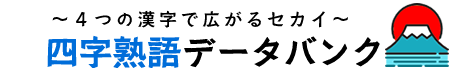▼これが『ダンス・ダンス・ダンス』から連想する四字熟語です

① 確固不抜(かっこふばつ)
意志がしっかりしていて動揺しないさまを、「確固不抜」といいます。
俗にいう鼠三部作の続編と位置づけられる今作『ダンス・ダンス・ダンス』。
物語は『羊をめぐる冒険』の舞台となった北海道のドルフィン・ホテルに戻ることから始まります。
新しい建物になり、かつての面影のなくなったドルフィン・ホテルで「僕」はユミヨシさんという女性に出会い、それがきっかけで羊男と再会します。暗闇の中に潜みながらずっと「僕」を待っていた羊男は、疲れてどうしようもなくなっている「僕」にこう言います。
「踊るんだよ。音楽の鳴っている間はとにかく踊り続けるんだ」と。
すでに多くのものを失ってしまっている「僕」は、さらにひどい状況に陥ったとしても「確固不抜」たる決意をもって踊り続けるしかないのです。
何故「僕」は踊り続けなければならないのか。
その答えを探すには、羊男のいう音楽が何の暗喩なのかを考えなければいけません。
「僕」を取り巻く人たちなのか、それとも時代の流れという不可逆的なものなのか。
奇妙で複雑なステップを踊りきった先に見える景色が、その答えを教えてくれるのかもしれません。
② 冬夏青青(とうかせいせい)
「冬夏青青」とは、松やコノテガシラといった常緑樹が夏も冬も青々と茂っていることから、節操が固く常に変わらないことのたとえです。
『ダンス・ダンス・ダンス』では時折、偏見的な文章が見られます。
それを顕著に表しているのが、ユキという少女との学校についての会話です。
「嫌な奴がでかい顔してる。下らない教師が威張ってる。はっきり言って教師の八〇パーセントまでは無能力者かサディストだ。あるいは無能力者でサディストだ」
そして、もし学校に行きたくないなら、「そういうのを嫌だと言う権利は君にあるんだよ。大きな声で嫌だと言えばいいんだ」と続きます。
この言葉の裏にあるのは資本主義社会や、権力社会に対するアンチテーゼなのかのしれません。
会社に置き換えれば教師ではなく上司が、政治に置き換えれば政治家が、その偏見の矛先になるのでしょう。
権力に興味をもつ人間が無能力者かサディストであるとすれば、そんな人間が作った社会の中で真っ当に生きていくためには「冬夏青青」たる態度で自分を貫くしか方法がないのだ、と読者に語りかけているのではないでしょうか。
たとえそれが、端から見て逃げだと思われたとしても。
③ 物換星移(ぶっかんせいい)
「物換星移」は、物事が変わり、歳月が過ぎゆくことの意味で、世の中が移り変わることをいいます。
ディズニーランドが開園し、学生の頃に聞いていたビーチ・ボーイズは前時代のアイコンとして使われ、ポパイやホットドッグ・プレスの推薦する役に立たない雑貨を買うことがある種のステータスになるような、高度資本主義社会。
そんな中、型落ちしたスバルと心を通わせて親密な関係をつくるような、前世代的な「僕」はどうやって生きていけばいいのでしょうか。
僕」はひょんなことから行くことになったハワイで、こつ然と消えた100%の耳をもつガール・フレンド、キキとすれ違います。
追いかけたあとに辿りいた部屋で6体の骨を見つけ、そこから物語は終焉へと向かうのですが、これは『ダンス・ダンス・ダンス』が終わりへ向かうだけではなく『風の歌を聴け』から始まった「僕」の終焉でもあります。
「どんなものでもいつかは消えるんだ。我々はみんな移動して生きてるんだ」
「僕」は諦めたような様子でそう言いながらも、加速していく「物換星移」の中で自分が消えないように必死で足掻いているようにも思えます。
現実の象徴であるユミヨシさんの存在があり、五反田くんというある意味で分身のような存在との別れも、足掻く切っ掛けになったのかもしれません。
そうしていくつもの喪失と再生を繰り返し、踊り続けることが出来たからこそ、最後の場面において様々な言葉の中から「ユミヨシさん、朝だ」という極めてポジティブな言葉を選べたのでしょう。
そこには今までのような闇はなく、新しい世界で生きていく、という決意が感じられるような情景が広がっているのです。