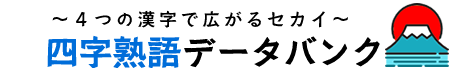▼これが聖徳太子から連想する四字熟語です

① 聡明叡知(そうめいえいち)
生まれたときから非常に賢く、物事を先まで見通し、真実を見極める力を持っていることを、「聡明叡智」といいます。「聡・明・叡・智」は、聖人の持つ四つの徳のことでもあります。
聖徳太子は、幼いころから大変に聡明で、多くの人の言葉を同時に聞き分ける異能を発揮したり、外来の文化を深く理解するなど、高い知性のあったことがうかがえるエピソードをたくさん残しています。
② 洽覧深識(こうらんしんしき)
知識がとてつもなく広く、博学であることを、「洽覧深識」といいます。
聖徳太子は、いち早く仏教について学び、その洽覧深識をもって、宗教としての本質的な性格と、文化的な意味合いとを深く理解し、国をまとめる考え方として取り入れようとした人であると言われています。
③ 薤露蒿里(かいろこうり)
「薤露」と「蒿里」は、ともに葬送の折にうたわれた挽歌の名であり、そのことから、人の命が極めてはかないことを言うようにもなりました。
聖徳太子は、極めて徳が高く、また有能な為政者でありましたが、四十八歳で、病死したといわれています。太子の亡くなる直前に、太子の母と妻も亡くなっており、また子孫である上宮王家も、のちに滅亡することとなります。薤露蒿里、人望の高かった聖徳太子の人生はかなさを思わずにはいられません。
※その他、十七条憲法第一条の「用和為貴(ようわいき」も有名です。